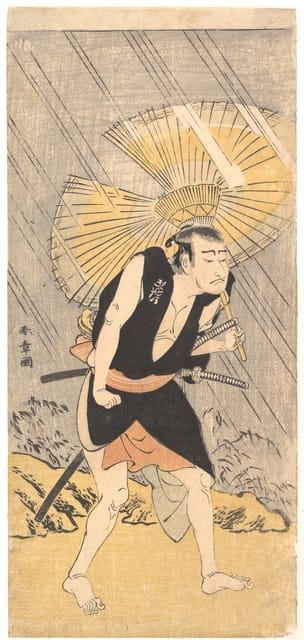これは勝川春章(享保11〜寛政4・1726〜93)の役者絵だ。
制作年は明和3(1760)年とあるから
9月の市村座「仮名手本忠臣蔵」の斧定九郎を描いたものだ。
定九郎の出る五段目は、山崎街道で与一兵衛を殺し、懐から大枚金を盗んだ定九郎が、
勘平の鉄砲に当って死ぬというだけの場面で、
客はこの場で弁当を食べるので弁当幕ともいわれている、捨て場だ。
定九郎の衣裳は、単なる頭巾に縞のどてらという人形芝居のままの山賊姿だ。
定九郎役をもらった稲荷町(大部屋)の中村仲蔵は、出世のチャンスとばかり役作りに取り組み、
この絵のような衣裳を考えたのだ。
定九郎は山賊に落ちぶれたとはいえ、もとは塩治家の家老の息子だ。
仲蔵はぼさぼさの月代で、どろりと汚れた黒羽二重の紋付を尻っぱしょりして、
草履を帯にはさみ、派手な鞘の刀を差し、ぼろ傘を手に素足で花道から登場した。
水をかぶって出たので、足もとに水がぽたぽたと垂れている。
弁当を食べていた客は仲蔵の姿にびっくり仰天、舞台の仲蔵に見入った。
仲蔵の定九郎は大当たりで、仲蔵はこれ一発で一躍名を馳せた。
以来定九郎にはこの姿が定着するのだ。
![]()
制作年は明和3(1760)年とあるから
9月の市村座「仮名手本忠臣蔵」の斧定九郎を描いたものだ。
定九郎の出る五段目は、山崎街道で与一兵衛を殺し、懐から大枚金を盗んだ定九郎が、
勘平の鉄砲に当って死ぬというだけの場面で、
客はこの場で弁当を食べるので弁当幕ともいわれている、捨て場だ。
定九郎の衣裳は、単なる頭巾に縞のどてらという人形芝居のままの山賊姿だ。
定九郎役をもらった稲荷町(大部屋)の中村仲蔵は、出世のチャンスとばかり役作りに取り組み、
この絵のような衣裳を考えたのだ。
定九郎は山賊に落ちぶれたとはいえ、もとは塩治家の家老の息子だ。
仲蔵はぼさぼさの月代で、どろりと汚れた黒羽二重の紋付を尻っぱしょりして、
草履を帯にはさみ、派手な鞘の刀を差し、ぼろ傘を手に素足で花道から登場した。
水をかぶって出たので、足もとに水がぽたぽたと垂れている。
弁当を食べていた客は仲蔵の姿にびっくり仰天、舞台の仲蔵に見入った。
仲蔵の定九郎は大当たりで、仲蔵はこれ一発で一躍名を馳せた。
以来定九郎にはこの姿が定着するのだ。